ニュース
2025-01-06
1/17(金)から、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下で、清原惟監督特集が開催!2025年1月17日(金)より、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下にて、清原惟監督の、映画館で初の特...
2024-07-09
7月14日(日)から上映がスタートするシネマ・チュプキ・タバタにて、トークイベント開催決定!全国での上映が続いている本作ですが、再び東京での上映が始まります。7月14日(日)から30日(火)まで、...
2024-05-22
『裸足で鳴らしてみせろ』工藤梨穂監督よりコメント到着!6月以降も、全国で続々と上映劇場が決定中。先日、大阪シネ・ヌーヴォ、横浜シネマ・ジャック&ベティでの上映が終了しました。ご来場いただいた皆...
2024-04-24
小田香監督からコメント到着!4月27日(土)より、横浜シネマ・ジャック&ベティ、大阪シネ・ヌーヴォで公開スタート『すべての夜を思いだす』の7週間にわたる、渋谷ユーロスペースの上映が終了しました。そして4月27日(土)...
2024-02-27
映画『すべての夜を思いだす』オリジナル・サウンドトラック発売決定&多摩にて映画公開記念コンサート開催決定。こんにちは。映画『すべての夜を思いだす』オリジナル・サウンドトラック発売決定&多摩にて発売記念コ...
2024-02-26
映画『すべての夜を思いだす』ユーロスペース初日と2日目の舞台挨拶、アフタートークが決定しました!映画『すべての夜を思いだす』ユーロスペース初日と2日目の舞台挨拶、アフタートークが決定しましたのでお知ら...
2024-02-22
『すべての夜を思いだす』 監督 清原惟さんインタビュー(後半) ーーたとえ自分が覚えていなくても、その記憶が消えてしまうわけじゃないこんにちは。本日は『すべての夜を思いだす』本作監督、清原惟さんと月永理絵さんのインタビュー対談の後半部分...
2024-02-18
『すべての夜を思いだす』インタビュー(前半) 清原惟監督・インタビュアー月永理絵さんーー映画をつくるために視点を選ぶというより、私たち自身がここにいることから映画の視点を見つけていく。こんにちは。本日は『すべての夜を思いだす』本作監督、清原惟さんと月永理絵さんのインタビュー対談を前後半に...
2024-02-18
『すべての夜を思いだす』の監督・清原惟さんの新作、旧作の3月上映が続々と決定。こんにちは、『すべての夜を思いだす』の監督である清原惟さんの新作、旧作の3月上映が続々と決まっています。...
イントロ
ダクション
街の中に積もり重なる無数の記憶と、誰かの一日が呼応する―。
同じ場所、同じ時間に共在する、世代の異なる3人の女性、それぞれの「ある日」。
高度経済成長期と共に開発がはじまった、東京の郊外に位置する街、多摩ニュータウン。入居がはじまってから50年あまりたった今、この街には静かだけれど豊かな時間が流れている。
春のある日のこと。誕生日を迎えた知珠(兵藤公美)は、友人から届いた引っ越しハガキを頼りに、ニュータウンの入り組んだ道を歩きはじめる。
ガス検針員の早苗(大場みなみ)は、早朝から行方知らずになっている老人を探し、大学生の夏(見上愛)は、亡くなった友人が撮った写真の引き換え券を手に、友人の母に会いに行く。
世代の違う3人の女性たちは、それぞれの理由で街を移動するなかで、街の記憶にふれ、知らない誰かのことを思いめぐらせる。
すでに多くの海外映画祭でも高い評価を得、2023年には日本公開を前に北米での公開も果たした本作の監督は、前作『わたしたちの家』で国内外から注目を浴びた清原惟。太陽の光が降り注ぎ、公園と団地がどこまでも続くかのような多摩ニュータウンを舞台に、人々の一見平凡に見える日常がいかに尊いものかを、あたたかく詩的な眼差しで捉えた。
3人の主人公を演じるのは、青年団のメンバーとして数々の演劇に出演してきた兵藤公美と、ロロや贅沢貧乏など演劇を中心に、演出家から多大な信頼をあつめる大場みなみ、そして、ドラマ、CM、映画など幅広い活躍をみせる見上愛。ほかに、俳優であり文筆家としても活躍する内田紅甘、アッバス・キアロスタミ監督の遺作『ライク・サムワン・イン・ラブ』の主演を務めた奥野匡、芥川賞作家の滝口悠生など、個性的な出演者たちが街に生きる人々を演じている。
高度経済成長期と共に開発がはじまった、東京の郊外に位置する街、多摩ニュータウン。入居がはじまってから50年あまりたった今、この街には静かだけれど豊かな時間が流れている。
監 督 紹 介
-
監督・脚本 清原 惟
映画監督、映像作家。
17歳の時に友人と映画をつくってから今まで、映画や映像をつくりつづけている。 監督作『わたしたちの家』(17)、新作『すべての夜を思いだす』(22)がベルリン国際映画祭フォーラム部門をはじめとする国内外の映画祭で上映される。最新作として愛知芸術文化センターオリジナル映像作品として制作した『A Window of Memories』がある。 ほかの活動として、土地やひとびとの記憶について、リサーチを元にした映像作品の制作をしている。
キャスト
-
兵藤公美
(山住知珠ちず 役)

神奈川県出身。桐朋学園大学演劇専攻科卒業。96年に青年団入団。
演劇での主な出演作には「日本文学盛衰史」、「思い出せない夢のいくつか」、青年団×パスカル・ランベール「KOTATSU」がある。客演で、Q「バッコスの信女-ホルスタインの雌」、情熱のフラミンゴ「ドキドキしていた」などに参加。映画出演作に『歓待』、『哀愁しんでれら』、『子供はわかってあげない』、『MADE IN YAMATO/まき絵の冒険』などがある。演劇・映画界で幅広い活躍をみせる。 -
大場みなみ
(谷本早苗 役)

大学卒業後、舞台での活動を本格的にスタート。気鋭監督や演出家からの信頼が厚く、舞台、映画、CMなどジャンル問わず活動している。近年の主な出演作に、舞台ロロ『オムニバス・ストーリーズ・プロジェクト(カタログ版)』、『メルセデス・アイス』、贅沢貧乏『わかろうとはおもっているけど』、映画『日曜日、凪』、『小さな声で囁いて』などがある。
-
見上 愛
(荻野夏 役)

2019年デビュー以降、映画・ドラマ・舞台・CMと幅広く活躍。近年の主な出演作に、Netflix『幽☆遊☆白書」、 MBS主演ドラマ『往生際の意味を知れ!』、NHK『きれいのくに」、映画『365km、陽子の旅』、映画『異動辞令は音楽隊!』などがある。2024年はNHK大河ドラマ『光る君へ」、KTV『春になったら」などの作品が控えおり、いま最も注目俳優。
音楽・ダンス
-
ジョンのサン:音楽

2002年に結成し、現在は各地に総勢12人ほどが在籍し、企画ごとで参加者、それぞれの担当楽器などを変えるなどの取り組みをしている。音楽作品は継続的に製作・発表しているが、それ以外の活動では、2021年から作・演出・出演のコントを4公演行い、2022年からは映画音楽も制作、『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』などがある。
-
ASUNA(アスナ):音楽

石川県出身の日本のサウンドアーティスト。干渉音の複雑な分布とモアレ共鳴に着目した「100 Keyboards」や膜鳴楽器の張力と振動の関係を扱った「Falling Sweets / Afternoon Membranophone」などの作品で海外のアート・フェスティバルから多数の招待を受け、これまで25カ国以上で展示/パフォーマンスを行う。並行した音楽制作では電子音を中心としながら様々なアコースティック楽器やオモチャ楽器による作曲作品から即興演奏まで行っている。
-
ESV:ダンス音楽

ななし、タンゴ、mado、moddkoiの4人で楽曲制作、ライブなどをする。
-
mado

ラッパー、トラックメーカー。楽曲制作やライブを行う。近年はジョンのサンにも参加。2023年12月に荒井優作との共作Single『砂』をリリース。
清原 惟監督
インタビュー
2023年12月1日・渋谷にて インタビュアー 月永理絵
――まずは、前作『わたしたちの家』から本作に至るまでの経緯を教えていただけますか。
清原:『わたしたちの家』をつくったあとに、PFFスカラシップに応募してこの企画が通ったんですが、実は当初考えていた物語は今とはかなり違う内容でした。世代の異なる三人の女性の話という点は同じですが、舞台は一軒のホテルで、宿泊客や従業員などそれぞれにまったく別の形で過ごす女性たちの一日を描く、という話でした。前作では一軒の家を舞台に二つのパラレルな世界を描いたので、今度はより大きな場所を使うことで、パラレル度具合をより複雑なものにしてみたかったんです。
ただ、実際にロケハンを始めてみると、限られた予算のなかで理想的なホテルを見つけるのは想像以上に難しいと気付かされました。そうしているうちに、今度はコロナ禍が訪れました。感染が拡大するなかでロケハンに行くのが難しくなったうえに、観光業であるホテルはコロナ禍で大きな打撃を受けていた。私が当初考えていた話は、閉業を迎えるホテルの最後の一日を描くもので、今それを描くならコロナのことを踏まえずには撮れない。そうした製作上の困難がいろいろあり、これは企画を変えるしかないと、もう一度初めから考え直すことになりました。その後多摩ニュータウンを舞台に考えた話があって、そこで兵藤公美さん、大場みなみさん、見上愛さん、という三人の主演が決まりました。ただこれも諸事情で中止となり、舞台と主演三人をもとにまた企画を立て直して、と進めるうちに、ようやく今の形で撮ることが決まった、というのがこれまでの経緯です。
――今の企画になるまでに、企画は二転三転されたんですね。
清原:ただ、その間もタイトルはずっと『すべての夜を思いだす』で変わらなかったんです。世代の違う三人の女性たちが触れ合うようで触れ合わない、という話の構造も残っていました。話自体は大きく変わったけれど、作品の根幹はずっとつながっていたのかなという気がします。
――今の映画の舞台として登場する街は多摩ニュータウンですよね。
清原 はい、今回は多摩ニュータウンという街自体をひとつの空間として撮りたいと考えて、その中でもわりと初期に造成されたエリアを使っています。ここは自分が幼稚園くらいのときに住んでいた街で、私にとって原風景的な場所でもあるのかもしれません。あとはやはりコロナ禍を経験してから、外に出たい気持ちが大きくなってきたように思います。実際に撮影するときも狭い室内より外の方が安心できるし、街へと出ていって、散歩をするように撮影をしたいという思いが強くありました。
――外の空間を撮るうえで、カメラの置き方や対象との距離の置き方も大きく変わっていったんでしょうか?
清原 それは変わりましたね。『わたしたちの家』のときは、室内でカメラが置ける場所が限られてしまうことを逆手にとったアプローチが多かったけれど、外に出てみると、どこにでもカメラを置けるし、どんな距離感で見ることもできる。無限の可能性が出てくるんです。前作が家にあわせた視点だったとすれば、今回は人の視点という要素が重要になるなと気づきました。
今回、ロケハンと言いながらほとんど散歩みたいにみんなで街を歩く時間がたくさんあったのですが、そこで撮影監督の飯岡幸子さんが撮ってくれた写真がどれも本当に素晴らしくて、ああ、この人が見ている世界を見たいなと思えました。映画をつくるために視点を選ぶというより、私たち自身がここにいることから映画の視点を見つけていく。今回の映画はそんなふうにつくっていったような気がします。
――清原さんだけでなく、飯岡さんの視点もこの映画の大きな要素になったわけですね。
清原:同様に、音響の黄永昌さんとの作業も映画にとって大きなことでした。黄さんは、撮影の合間に気づくといつもふっと姿が消えていて、その間にみんなの見えない場所で素材となる音を録音していました。この映画には、そうやって黄さんが集めた街のいろんな音が積み重ねられていると思います。
――女性の生き方としてもそれぞれのバリエーションがあっておもしろいですよね。それぞれのキャラクター設定はどのようにつくりあげていったんでしょうか?
清原:ちょうど脚本を書いていた時期に、私も映画を撮るために自ら仕事を辞めたのですが、ハローワークという空間の不思議さに気付いたり、仕事をしていないことで社会的に自分がどう見られるのかを改めて考えさせられたりしました。そういう経験から知珠さんのキャラクターが生まれてきたように思います。早苗さんに関しては、ガスの検針員の方って意外と日常で目にする機会が多いんですよね。なぜか働いているのは女性の方が多くて、一日中外を歩きながら、ときには家の中や団地の共有部分に立ち入って仕事をしている。外部の人間でありながら若干家の内部に侵食している感じがおもしろいな、と思ってこの職業を描いてみようと思いました。
――冒頭の、ジョンのサンのみなさんが話している場面もおもしろいですね。
清原:あそこは、流れだけ決めておいて、あとはみなさんに自由に話してもらいました。冒頭、早朝の街の風景カットが連続しますが、同じように彼らが集う場面も街の風景の一部として撮りたくて。そもそも彼らに出てほしかった理由は、音楽をひとつの登場人物として映したかったからです。朝、街に集まって練習をしているバンドの人たちがいて、彼らが今も街のどこかで音を鳴らしているかもしれない。そういう時間が続いているような感じで、あのシーンを撮ろうと思ったんです。
――映画には、三人の女性が抱える暗い影がかすかに見えてきますよね。特に夏さんの場合は、死んでしまった友人の記憶に導かれているわけですが、こうした暗い影について、監督は意識して書かれていたんですか?
清原:「死」にまつわることを取り入れたいとは、当初から考えていました。というのも、多摩ニュータウンは基本的に生活に必要な機能がほぼすべて揃った形で開発されているのですが、実は火葬場やセレモニーホールのような、「死」をあつかう場所は都市計画の中に含まれていないからです。そうした施設があるのは、街のなかで何らかの理由から区画整理されずに残った「間(はざま)」のエリア。でもここで亡くなった人たちももちろんいるだろうし、確実に死は存在しているじゃないですか。この一見「死」が排除されたように見える場所で、「死」がどういうふうに取り扱われるのかを描きたいと思ったんです。
こんなふうに、実際の街から生まれてきた要素はすごく多いと思います。今回は、脚本を書く段階でとにかく街をたくさん歩き回っていて、ほとんど場所の当て書きという感じで書いていきましたから。
――住人の誰かが行方不明になると、街全体にアナウンスが流れるというエピソードも、実際にニュータウンで見聞きしたことから生まれたのですか?
清原:あのアナウンスは、私の地元の街でよく流れていて、それがすごく印象に残ったんです。誰かがいなくなったことを街全体が知っている感覚が不思議だったし、こんなに頻繁に人っていなくなるんだなってことも気になっていました。
――行方不明になった高田さんと早苗さんのやりとりにはドキッとしました。二人は一緒に歩いて同じものを見ているはずなのに、実際に見ている景色は明らかに違っている。それは高田さんが記憶の中の街を見ているからで、そういう人々の記憶の重なりとずれみたいなものが、あのシーンに顕著に出ている気がしました。写真やビデオ映像もいろいろ出てきますが、やはり「記憶」というテーマは、清原監督にとって大事な主題なのでしょうか?
清原:写真や映像って、自分とは別の、外部の記憶装置としてあるんですよね。その一方で、写真や映像が自分の記憶そのものとして存在していることもあるのが、私はずっと面白いなと考えていました。私が小学生くらいのときに、自分が赤ちゃんの頃の写真を見たことがあって、その写真を見ながらあたかも「この頃のことを覚えている」と感じたことがあったんです。それが捏造された記憶だと気付いたのは、それからさらに年月が経ってもう一度同じ写真を見たときのこと。写真を見ながら、実際には知っているはずのない記憶がよみがえってきて、写真によって、自分のもうひとつの記憶が再生されていく瞬間を体験したんです。
自分自身は忘れてしまったのに、他人の方がよく覚えている、ということもよくありますよね。たとえ自分が覚えていなくても、その記憶が消えてしまうわけじゃない。別の誰かが覚えていたり、写真や映像という装置によって記憶は存在している。そういう感覚が不思議であり、おもしろいなとずっと考えていて。だから自分が映画をつくるときは、記憶に関するいろんなアプローチをしているのかもしれません。
――夏さんが友達と訪ねる博物館も印象的でした。あそこで彼女たちが見るのは、あの場所のさらにもっと昔にあった記憶の連なりみたいなものですよね。
清原:あそこは多摩センター駅の目の前にある、多摩地域で出土したものを中心に置いている東京都埋蔵文化財センターです。映画『平成狸合戦ぽんぽこ』が有名になったこともあり、多摩ニュータウンというと人があまり住んでいなかった森や農村地帯を開発してつくった街というイメージが強いですが、調べていくと、実はもっと昔には人がこの地に住んでいたことがわかって、別に突然現れた街ではないんだと気づきました。まさに、地層みたいなものが積み重なってできた場所なんですよね。
――なるほど、街自体が巨大な記憶装置とも言えますね。清原監督のお話をうかがって、この映画が、空間においても、時間においても無限の広がりを持った映画なのだとよくわかりました。
高度経済成長期と共に開発がはじまった、東京の郊外に位置する街、多摩ニュータウン。入居がはじまってから50年あまりたった今、この街には静かだけれど豊かな時間が流れている。
-

第73回ベルリン国際映画祭
フォーラム部門 正式出品 -

第13回北京国際映画祭
フォワード・フューチャー部門
審査員特別賞受賞
- ニュー・ディレクターズ/ニュー・フィルムズ 2023 正式出品
- 第23回ニッポン・コネクション ニッポン・ビジョンズ部門 正式出品
- 第12回クリチバ国際映画祭 インターナショナル・コンペティション部門 正式出品
- 第23回台北映画祭 アジアン・プリズム 部門 正式出品
- 第71回メルボルン国際映画祭 アジア・パシフィック部門 正式出品
- 第71回サン・セバスチャン国際映画祭 サバルテギ・タバカレラ部門オープニング上映
- 第29回釜山国際映画祭 A Window on Asian Cinema部門 正式出品
- 第20回香港アジア映画祭 ニュー・タレント・アワード部門 正式出品
- 第1回サウス・バイ・サウス・ウェスト・シドニー ビジョンズ部門 正式出品
- 第64回テッサロニキ国際映画祭 フィルム・フォワード・コンペティション部門正式出品
劇場情報
| 地域 | 劇場 | 電話番号 | 上映日程 |
|---|---|---|---|
| 東京 | Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下 | 050-6875-5280 | 上映終了 |
| 北海道 | シアターキノ | 011-231-9355 | 上映終了 |
| 東京 | ユーロスペース | 03-3461-0211 | 上映終了 |
| 東京 | CINEMA Chupki TABATA | 03-6240-8480 | 上映終了 |
| 千葉 | キネマ旬報シアター | 04-7141-7238 | 上映終了 |
| 群馬 | シネマテークたかさき | 027-325-1744 | 上映終了 |
| 神奈川 | シネマ・ジャック&ベティ | 045-243-9800 | 上映終了 |
| 福島 | いわきPIT | 0246-22-7777 | 上映終了 |
| 福島 | 湯本駅前ミニシアターkuramoto | 080-2109-6385 | 上映終了 |
| 大阪 | シネヌーヴォ | 06-6582-1416 | 上映終了 |
| 神戸 | 元町映画館 | 078-366-2636 | 上映終了 |
| 愛知 | ナゴヤキネマ・ノイ | 052-734-7467 | 上映終了 |
| 長野 | 上田映劇 | 0268-22-0269 | 上映終了 |
| 長野 | 松本CINEMAセレクト | 上映終了 | |
| 広島 | 横川シネマ | 上映終了 | |
| 大分 | シネマ5 | 097-536-4512 | 上映終了 |
| 熊本 | Denkikan | 上映終了 | |
| 鹿児島 | ガーデンズシネマ | 099-222-8746 | 上映終了 |
兵藤公美 大場みなみ 見上 愛
遊屋慎太郎 能島瑞穂 内田紅甘 奥野 匡 川隅奈保子 中澤敦子
佐藤 駿 滝口悠生 高山玲子 橋本和加子 山田海人
小池 波 渡辺武彦 林田一高 音道あいり 松本祐華
脚本・監督:清原 惟
第26回PFFスカラシップ作品
製作:矢内 廣、堀 義貴、佐藤直樹
プロデューサー:天野真弓
ラインプロデューサー:仙田麻子
撮影:飯岡幸子
照明:秋山恵二郎
音響:黄 永昌
美術:井上心平
編集:山崎 梓
音楽:ジョンのサン&ASUNA
ダンス音楽:mado&supertotes、E.S.V
振付:坂藤加菜
写真:黑田菜月
グラフィックデザイン:石塚 俊
制作担当:田中佐知彦 半田雅也
衣裳:田口 慧
ヘアメイク:大宅理絵
助監督:登り山智志
監督応援:太田達成
監督助手:岩﨑敢志
撮影助手:村上拓也
照明助手:平谷里紗
美術助手:庄司桃子
美術助手:岡本まりの
衣裳助手:中村祐実
制作進行:山口真凛
制作応援:小川萌優里
制作デスク:鈴木里実
デジタルマネージメント:望月龍太
ロケーションコーディネーター:柴田孝司
車輛部:多田義行
撮影応援:西村果歩
照明応援:本間真優
美術応援:登り山珠穂
衣裳応援:松岡里菜
メイク応援:桑原里奈
スタジオエンジニア:大野 誠
カラーグレーディングオンライン編集:上野芳弘
オンライン編集:野間 実
デジタルシネママスタリング:深野光洋 高津戸寿和
CG合成:細沼孝之
ポスプロコーディネー:中島 隆
タイトル制作:津田輝王 関口里織
 製作:PFFパートナーズ(ぴあ、ホリプロ、日活)/一般社団法人PFF
製作:PFFパートナーズ(ぴあ、ホリプロ、日活)/一般社団法人PFF
制作プロダクション:エリセカンパニー
配給:一般社団法人PFF
©2022 PFFパートナーズ(ぴあ、ホリプロ、日活)/一般社団法人PFF
©2022 Pia/HoriPro Inc./NIKKATSU/PFF General Incorporated Association, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex


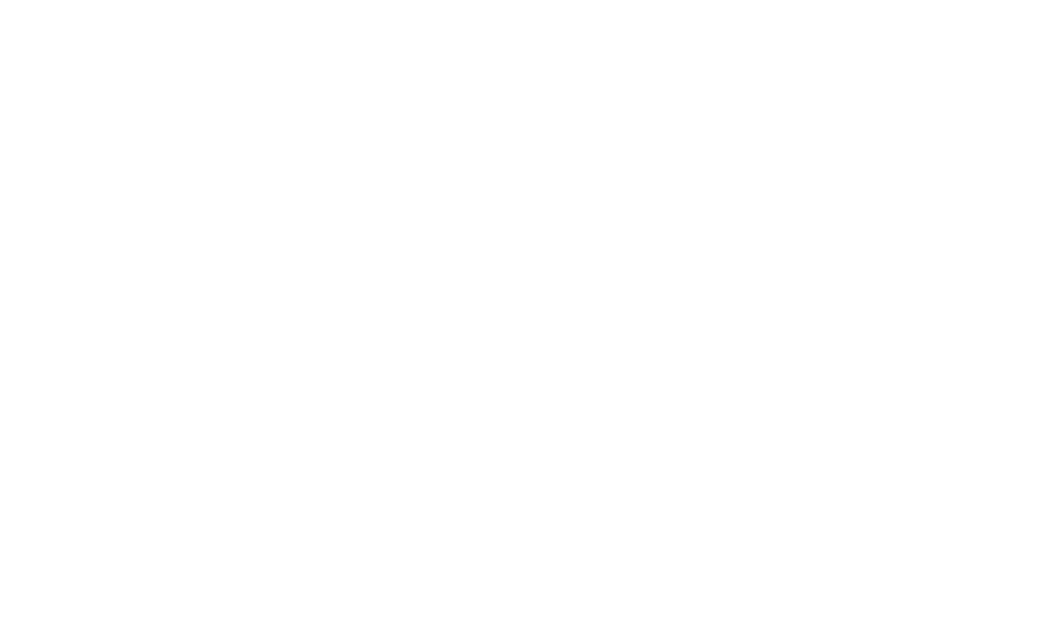


コメント
人々の間に流れる空気が、素晴らしかった。
―――アルノー・デプレシャン(映画監督)
3人のかすかな気配が、画面に映らない3人を映し出す。
それはまるで、幼い頃のホームビデオに映らない、大切な存在のように。
―――青柳菜摘(アーティスト)
冒頭のカットから、これは特別な映画だ、と直感しました。
3人の女性の一日を、離れたところから、ゆったりと見つめる。
その「場所」の素晴らしさにときめきながら、一緒に歩いていく。
――――クリスティーナ・ノード
(ベルリン国際映画祭 フォーラム部門・元ディレクター)
人が忘れても道は覚えている。今日という日が、あらゆる時間につながっていると感じる映画でした。
―――朝吹真理子(小説家)
忙しく生きていたらこぼれ落としてしまいそうな、ゆっくり生きてる人にだけ見える宝物みたいな瞬間が、ニュータウンという街を軸に星座みたいに散らばっている。私たち観客は、街を行き来する魅力的な登場人物たちに連れられて、その星座をひとつひとつ拾い集めることになる。
――――石原海(アーティスト/映画監督)
緑と黄緑の何と美しい、膨らむ一面の木、形作られた道の草、土混ざる淡い芝生。鳥の鳴き声、風の音、光と暗さが私たちにも迫る。その中に穏やかで不穏な彼女らの日常、得て失ってきた時間が流れる、それも私たちに迫る。
―――井戸川射子(詩人/小説家)
かつてそこにあった物たちが、出来事たちが、記憶たちが、誰にも語られることもなく、至る所に生ずる亀裂から噴出してくる。それらは過去や未来もなく、現在に同時に存在している。権力とは無縁の、小さな無名の記憶たちの救済。いまの日本だからこそ見えてくる風景だ。
――――ヴィヴィアン佐藤(芸術家/非建築家)
バスの車窓から見た景色のようにどこまでも横にずれていく。偶然の出来事が重なりながらどこにもつながらない。こういう中心を欠いた豊かな時間が、人生には確かに存在していると思った。
―――カゲヤマ気象台(劇作家/演出家/円盤に乗る派)
魅力的なダンスシーンがある映画が好きなんですが本作はまさにそうです。ダンスシーンは映画の本筋には大体関係ないけれど、そもそも私たちが生きている時間には本筋なんてないですよね。この映画の時間の中にずっといたいと思いました。
――――金川晋吾(写真家)
ある1日の営みや喜びと悲しみ、偶然の出会いを通して、映画は見事に私たちを深い思索へと導いていく。いかに私たちの人生は予期しない形で進み、時間の中で関わり合い、その瞬間が積み重なって意味深いものになりうるか。いろいろなことを考えさせられる、そして静かに心に残る作品だ。サウンドトラックも素晴らしい!
―――グレゴリー・オーク(『aftersun/アフターサン』撮影監督)
街は見知らぬ人々の記憶の総和、視認不可能なあらゆる死と生が蠢く場所。
『すべての夜を思いだす』は、画面に漂流する言葉なき空気でそれを伝える稀有な映画だった。
――――児玉美月(映画批評家)
なんでもないように見える特別な1日。
その日を乗り越えようとするあなたを、見知らぬ誰かが覚えていてくれるかもしれない。
気づいてくれた人がいたんだよ、とそんな眼差しで、すれ違う人同士が描かれていく。
だから、彼女たちがひとりでいても、孤独ではない夜が訪れる。そして、この1日を見届ける私たちに、救われる思いがあることを教えてくれる。
―――小森はるか(映像作家)
誰かに誘われたい気持ちと、ひとりでいたい気持ちの間にある感情に我々は名前をつけないまま、ないことにしている。
それを音楽にしようとするのがジョンのサンで、映画にしようとしたのが本作、ということかもしれない。
違ってもかまわん。傑作に変わりない。
――――Summer Eye/夏目知幸(ミュージシャン)
心地のよい時間がながれている映画だ。
それぞれの目的を持つ3人の女性が、古くて新しい多摩ニュータウンのそこここにあらわれる。
まるでニュータウンの精霊のように――。
―――中澤日菜子(小説家/劇作家)
画面に木や草がはみ出してくる。それはかつて人間に消されたもの。削られた山に建てられた団地でそれらだけが濃く、人間は薄い。このまま映画から人間が消えていくんじゃないかと思った。かつてこうして人間がいたんだよ、というとき見るのはこの映画のような風景かもしれない。
――――山下澄人
(小説家)
人々はお互いを知らぬまますれ違い、見つめあい、想像しあう。そこには土地の歴史も死者も、観客であるこの私も巻き込まれる。私はこの映画の特に後半をかつてない動揺とともに見た。ここにすべてがあると感じた。
―――山本浩貴(小説家/デザイナー/いぬのせなか座主宰)
引き込まれる空気感、美しく完璧に切り取られた絵、端々まで命が宿っている。
スクリーンに流れていく時間、何処かで見たかも知れない風景やシチュエーション。
ふと立ち止まり、日常――"生きる"ということ、我々の物語に共鳴する。
――――米田知子(写真家)
あった事、あったかもしれない事、
気づかないけど静かに交差している事、
この感情を久しぶりに思い出した。
―――渡辺花(ビジュアルアーティスト/tamanaramen)
縄文人が聞いた土鈴の音を、
2024年を生きるじぶんたちが聞けるように、
朝の公園でバンドが鳴らす音たちや、探し人の町内放送は、
復元され、再生されるだろうか。
未来の、最上層にあるニュータウンで。
土地に、風が、人生が、音が、とおる。
記憶になる。
各々が独立して立ちながら、
空間/土地に和するイメージの心地よさに、
なぜときどき一抹の切なさも感じるのだろう。
リサイクル店のコップも、
現像された写真に遺されたイメージも、
過去を帯びるものだけど、誰かが見て、誰かが触れて、
その存在を更新していく。
――――小田香(映画作家)
誰かが生まれた日に誰かが亡くなってしまうように、人はことごとくすれ違う。
そんな無数のねじれの位置を生きている彼女たちが、見知らぬ誰かのダンスに自らの身体を突き動かされた光景をずっと忘れない。
ありえたかもしれない出会いや叶わなかった再会に思いを馳せながら、
私たちはいつか死ぬけどそれでも生まれてきた。
この映画はあたりまえにみんなに誕生日があることを思いださせてくれるから、ふいに泣き出しそうになってしまう。
―――工藤梨穂(映画監督)